近年、腸内フローラの研究が進み、体重の増加や減少に関係する細菌が存在することが分かってきました。
よくネット上では「デブ菌」や「ヤセ菌」などと言われているようですね。
まだまだ謎の多い分野で、現在も様々な研究が進められていますが、今回はデブ菌とヤセ菌について現時点で分かっていることをお伝えしていきたいと思います。
※当記事は管理栄養士の服部明日香が執筆しました。
Contents
デブ菌とヤセ菌が広まったきっかけはファーミキューテス門とバクテロイデーテス門
私たちがデブ菌やヤセ菌を知るきっかけになったのは、2006年、科学誌Natureに掲載されたWashington大学のJeffrey Gordon教授らによる研究報告でした。
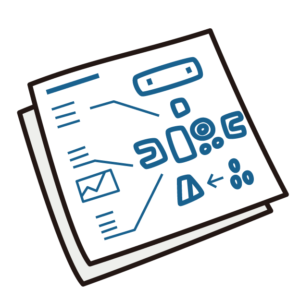
この研究では、太っている人と痩せている人それぞれの腸内フローラの比率を見てみたところ、太っている人の腸内フローラではファーミキューテス門が多く、痩せている人ではバクテロイデーテス門が多いことが分かりました。
さらに、太っている人が低カロリー食でダイエットをしたところ、体重減少とともに、バクテロイデーテス門の細菌数の比率が高くなったというのです。
このことから、ファーミキューテス門には体重増加に関係のある細菌、バクテロイデーテス門には体重減少に関係のある細菌がいるのではないかと話題になりました。
また、この研究結果が報告される前は、腸内フローラの研究では免疫に関連したものが多かったことも、一目注目を浴びるきっかけとなりました。
腸内フローラはデブ菌かヤセ菌しかいない!?
私たちの腸内フローラの80%~90%はファーミキューテス門かバクテロイデーテス門に分類されています。
ここまでの話を聞いてみると、腸内フローラのほぼ全てがデブ菌かヤセ菌ってこと!?と思ってしまいますよね。
しかし実際はそういうことではなく、ファーミキューテス門、バクテロイデーテス門それぞれの細菌のうち、ごく一部が体重増加や減少に関係しているだけなのです。
ファーミキューテス門、バクテロイデーテス門っていう名前の腸内細菌がそれぞれいるってことじゃないの?と疑問に感じた方はいらっしゃらないでしょうか。
また、~門の、「門」ってなに?という方もいらっしゃらないですか?
私は初めてこの細菌を知ったとき、このような疑問にぶち当たりました。
と、いうことで、一旦「門」について説明します。
先程から言っている、ファーミキューテス門やバクテロイデーテス門の「門」とは、生物を分類するときのグループ名です。
この「門」からさらに「綱」「目」「科」「属」「種」の順の階層に分類されます。
高校で例えると、~~高校という大きい括りが「門」、普通科やスポーツ学科、商業科などの各科が「綱」、それぞれの学年が「目」、各クラスが「科」、クラス委員長などの役割が「属」、各生徒が「種」というように分類するということです。
分からなくなってしまった方は、この例えは聞かなかったことにしてください。
このように、細菌の場合もそれぞれの細菌は「門」に分類されており、腸内細菌は「バクテロイデーテス門」、「ファーミキューテス門」、「アクチノバクテリア門」、「プロテオバクテリア門」の4つが大半を占めています。
バクテロイデーテス門には有名な細菌はいませんが、多数の種類の細菌が存在します。
ファーミキューテス門には、ヨーグルトや乳酸菌飲料に含まれている乳酸菌、納豆に含まれている納豆菌などがいます。
また、プロバイオティクスとして使用されている乳酸菌の一種も存在しています。
ここでもう一度言っておきますが、乳酸菌や納豆菌がファーミキューテス門に分類されているからといってデブ菌である、ということではありません。
あくまでも、それぞれの門のなかにデブ菌やヤセ菌が存在する、ということなのです。
デブ菌・ヤセ菌の正体は?
それでは、そのデブ菌・ヤセ菌とは一体なんという名前の細菌なのか?
実は、現時点ではそれぞれの門のどの細菌がデブ菌・ヤセ菌なのかは分かっていないのです。
ただ、冒頭でお話した通り、太っている人・痩せている人それぞれの腸内フローラを見てみると、太っている人はファーミキューテス門が多く、痩せている人はバクテロイデーテス門が多かった。
太っている人が低カロリー食でダイエットをしたら、体重減少ともにバクテロイデーテス門の比率が高くなった、ということが分かっているのです。
これは、生活習慣を改善すれば、体重が減少するだけでなく、身体も太りにくい体質に変わっていくということです。
相反する報告も!?
上記の研究結果では、太っている人はファーミキューテス門が多く、痩せている人はバクテロイデーテス門が多いということでしたね。
しかし、その後この結果とは相反する報告もあり、必ずしもどの研究結果も一致するとは限らないようなのです。
ただし、太っている人の腸内細菌は偏りがあり、痩せている人の腸内細菌は多様性があることが報告されています。
腸内細菌は元々体内に存在する細菌ですが、普段の食事から摂取することができる細菌も数多く存在します。
いつも同じものばかり食べない、肉・魚・野菜・大豆製品や発酵食品等様々なものを日頃から食べることが、腸内細菌の多様性に繋がり、太りにくい体質になっていくのかもしれません。
デブ菌とヤセ菌 記事執筆者情報
服部明日香

【経歴】
地方女子大学卒業 管理栄養士
化粧品OEMにて研究開発
大学在学時には同学科の友人10名で食育推進サークルを設立しました。
このサークルでは、外部の方々からの依頼を受け、レシピ作成や調理実習を混じえた食育などを行いました。
①某企業様からの依頼
アカモク(ぎばさ)を使用したレシピを3種類作成(アカモク入りパン、キッシュ、炊き込みご飯)
上記のレシピや調理の様子は、冊子に写真付きで掲載されました。
②某一般社団法人様からの依頼
東日本大地震を経験した点から災害食を考えてほしいとのことで、味噌玉を提案(お湯をかけるだけで出来る味噌汁の素)
また、食育イベントとして、幼稚園の年長~小学生を対象に災害食作り実習を実施。
(味噌玉の作り方もお伝えし、一緒に作って試食しました)
卒業後、医療機器メーカーにて営業として勤務した後、現在は化粧品OEMにて研究開発をしています。
また、フリーランスの管理栄養士として活動している友人のお手伝いもしております。
具体的な活動は下記の通りです。
①横浜港で開催された某イベントで山形県産のりんごとりんごジュースの販売。
(目的:東北の食材を紹介し、来場者の方々に購入していただくことで生産者を応援する)
②某一般社団法人様との共同で、小学校中~高学年とその保護者を対象にした、わかめの食育イベントの実施。
(目的:三陸の水産物やその美味しさを知ってもらい、水産物の消費量を上げること)